相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
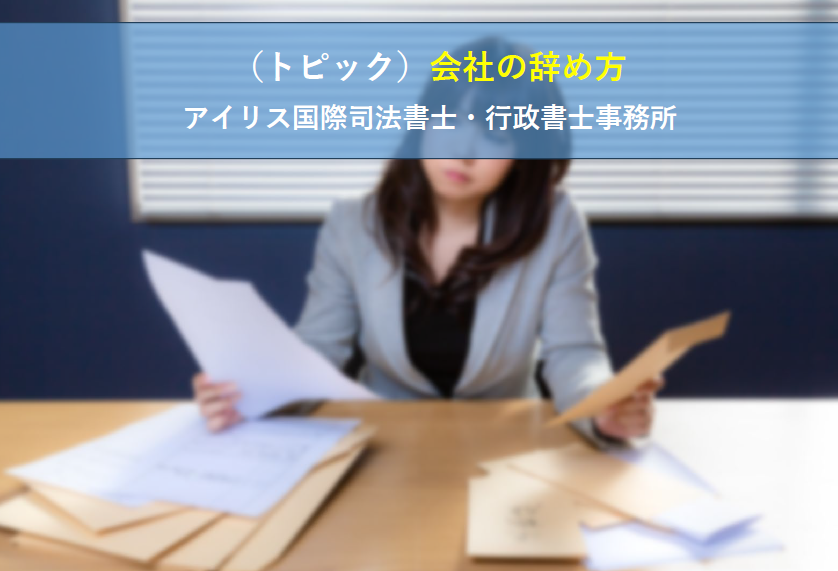
先日、とある方とお会いする機会があり、その方が独立して事業を始めるということで、会社に退職願を申し出たところ、経営者の方にめちゃくちゃ切れられた、というお話を聞きました。私自身も、いままで様々な業種を渡り歩いてきて、会社を辞めるときにドライな感じだったり、恫喝に近いような脅しを受けたりと両手以上の経験がありますのでお話をしたいと思います。
目次
1.法律上いつまでに退職願を出すべきなのか
2.なぜ、辞めると経営者は怒るのか
3.恫喝された場合の対処法
4.まとめ
1.法律上いつまでに退職願を出すべきなのか
期間の定めのない雇用、つまり正社員として雇われている一般的な正社員の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。
また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。
ただし、期間の定めのある雇用、契約社員などの場合は別です。
雇用契約を結んでから1年以内は、やむを得ない事情がないかぎり退職できません。
「(民法627条)
第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
第2項 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。」となっております。
2.なぜ、辞めると経営者は怒るのか

この点については、人によってさまざまな見解があると思うのですが、総じて言えることは、退職願を出した方が重要なポジションにあるなど、経営者が「当てにしていた」方なのではないかなと思います。私も多くの経験をしてきましたが、組織の規模が大きくなると、結構ドライで、退職願を出せば問題なく辞められます。逆に組織規模が小さいと、引き留め工作がうっとうしかったり、経営者に切れられる場面が多かったような気がします。
3.恫喝された場合の対処法
すぐに「労働基準監督署」に相談します。「労働基準監督署」に連絡するのは、「そうかそうか、大変だね。うちが解決してあげるよ。」なんてことにはまずはなりません。労働同基準監督署は労働基準法に違反している明確な証拠がないと深く相談にのってもらえません。ただ、嫌みを言われただけでは、まだ相談に乗ってくれるレベルではありませんから。それではなぜ、連絡する必要があるのかと言いますと、「後でもめたときの証拠づくり」です。公的な機関なので、相談すればその記録は保管されます。なので、恫喝を言われたらすぐに相談の連絡をしておくべきだと考えます。
私の場合の恫喝は、「街を歩けなくしてやる。」的なことを言われました。勿論労働基準監督署にすぐに連絡をして、その後は退職願を出し普通に仕事をして、引継ぎの打診があったので引継ぎをしましたが、退職日ぎりぎりに行い、引継ぎの最後には「解らないことがあったら、またお願いします。」と言われたので、「私、退職後は絶対に来ませんよ、ここに。」と言いました。
また、とある会社を退職した後、以前所属していた部署から「お前が導入したシステムで問題が起こっているから、今すぐ来てくれ。」と言われましたので、「業者に連絡してください。私は既に退職した人間なので雇用関係はありません。それでも来いという根拠がわかりません。仮に、どうしても必要な人材であるなら、なぜ辞めるときに反対しなかったんですか?」と質問すると電話を切りました。ご都合くんで使おうとしたのでしょうか?それはルール違反だと思います。一度でも対応したなら、次も次もと要求が増加していきます。給料ももらっていないのに要求にこたえる義理はありませんから、きっちり断るのが筋だと思います。

4.まとめ
今回は、雇用者目線での「退職」についてお話をしてきました。経営者の方も話し合いでは解決できない事情が退職者にはあるということを理解しておいた方がいいかもしれませんね。私のケースでいうと、会社を辞めるタイミングは、「将来」を考えて行動している場合が多いです。「お金」の面だけなら話し合いも通用するかもしれませんが、その人の未来まで奪う権利は、誰にもありませんからね。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「法律は知っている者の味方」という考え方は、特に相続において重要な意味を持ちます。相続の手続きにおいて、法定相続人は相続財産というプラスの財産を受け取る権利だけでなく、借金などの負の遺産を引き受ける義務も存在します。つまり、相続は財産だけではなく、被相続人(亡くなった人)の負債も含む全ての資産・負債が対象となるため、「負の遺産を受けたくないが、正の財産だけ欲しい」という要求は法律上通るものではありません。
2024年4月から相続登記が義務化されることにより、不動産の相続手続きを放置することができなくなりました。これにより、相続人は不動産の名義変更を行わなければならず、多くの方が自分で相続登記を行おうと考えるケースも増えています。しかし、単純な相続ならばともかく、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が必要な場合には、手続きが非常に複雑化し、専門知識が求められます。こうした場面で、司法書士という専門家の存在が重要になってきます。
生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、2024年(令和6年)1月1日以降の税制改正により、これまでと異なる規定が導入されました。特に「組戻し」期間の変更や課税対象に影響を与えるため、慎重に進めることが必要です。ここでは、重要な3つの注意点に絞って解説します。