相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年3月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
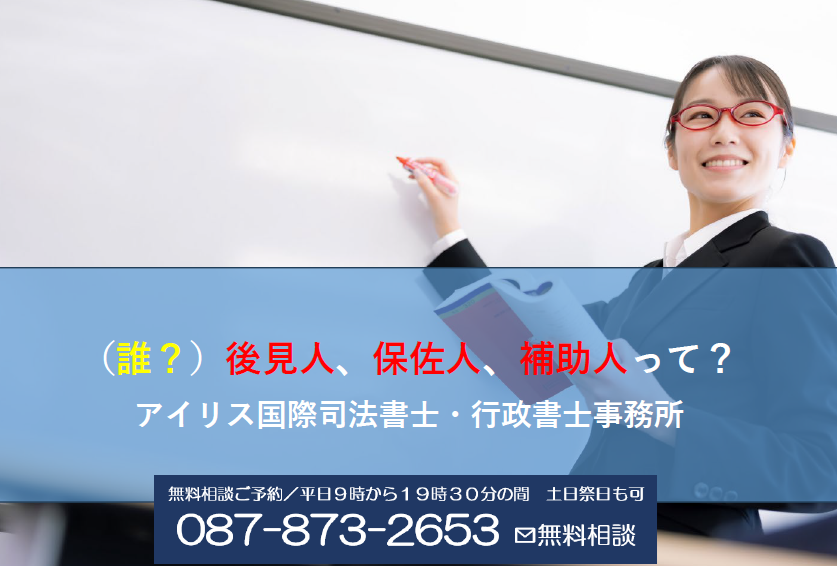
「後見人」「保佐人」「補助人」は、認知能力の低下や精神的な障害により、日常生活や財産管理に支障をきたしている人々を支援するために設けられた法的な支援者です。これらは成年後見制度(せいねんこうけんせいど)と呼ばれる制度に基づいており、支援の程度や内容が異なります。以下では、各役割の違いとその機能、選任方法、権限と義務、具体的な役割について詳しく説明します。
目次
1. 後見人(こうけんにん)
2. 保佐人(ほさにん)
3. 補助人(ほじょにん)
4. 制度の選択と運用
結論
1. 後見人(こうけんにん)

1.1 概要
後見人は、認知症や精神的障害、知的障害などによって判断能力がほとんどない人(被後見人)を支援する役割を果たします。成年後見制度の中でも、最も強い支援を提供する位置づけです。後見人は、主に財産管理や日常生活の様々な決定を被後見人に代わって行います。
1.2 選任方法
後見人は、家庭裁判所の申し立てによって選任されます。親族や市町村などが申し立てを行い、裁判所が適任者を後見人として選任します。後見人には、被後見人の親族が選ばれることもあれば、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選ばれることもあります。
1.3 権限と義務
後見人は、被後見人の財産全般を管理し、必要な契約の締結や支払い、収入の管理を行います。また、被後見人の生活を守るため、住居や介護サービスの選定、医療機関への入院手続きなども行うことができます。後見人には、被後見人のために誠実に行動しなければならない義務があり、財産を適切に管理する責任があります。
1.4 利点と課題
後見人の利点は、判断能力が著しく低下している人を総合的にサポートできる点です。一方で、後見制度は利用する際に費用がかかることがあり、また被後見人の自由が制約される面もあります。
2. 保佐人(ほさにん)

2.1 概要
保佐人は、判断能力が著しく不十分であり、後見ほどではないが、日常的な財産管理や法律行為に支障をきたしている人(被保佐人)を支援します。後見人と比べると、支援の範囲はやや限定されますが、重要な契約や財産の処分に関しては、保佐人の同意が必要とされます。
2.2 選任方法
保佐人も家庭裁判所によって選任されます。親族や市町村が申し立てを行い、裁判所が被保佐人の利益を考慮して選びます。後見人と同様に、専門職が選任されることもあります。
2.3 権限と義務
保佐人の役割は、被保佐人が単独で行うと不利益を被る可能性がある法律行為に対して同意を与えることです。具体的には、高額な財産の処分や借入契約、保証契約などが該当します。保佐人の同意がないままこれらの行為を行うと、無効となる場合があります。また、裁判所の許可を得ることで、より広範な財産管理を行うことが可能です。
2.4 利点と課題
保佐人の制度は、判断能力が部分的に低下している人に対して柔軟な支援を提供する点で有効です。ただし、後見制度と同様、利用には費用がかかることや、手続きが複雑であることが課題です。
3. 補助人(ほじょにん)

3.1 概要
補助人は、判断能力が不十分であり、一部の法律行為に支援が必要な人(被補助人)を支えるために選任されます。後見や保佐に比べて、支援の範囲がさらに限定されており、被補助人が単独で行える範囲が広く残されます。
3.2 選任方法
補助人の選任も家庭裁判所によって行われますが、被補助人本人の同意が必要です。被補助人がどのような支援を必要とするかについて、本人の意思を尊重して決定されるため、柔軟な運用が可能です。
3.3 権限と義務
補助人の役割は、被補助人が特定の法律行為を行う際に、その行為を支援することです。補助人の権限は、裁判所が定めた範囲に限られ、補助人の同意が必要な行為が限定されます。被補助人は基本的には自分で日常生活を営むことができるため、補助人の関与は最小限に抑えられます。
3.4 利点と課題
補助人制度の利点は、判断能力が部分的にしか低下していない人に対して、必要な支援だけを提供することで、本人の自立を尊重できる点です。一方で、支援が必要な範囲が限られているため、財産管理や法律行為においてトラブルが発生するリスクも残ります。
4. 制度の選択と運用
成年後見制度は、後見人、保佐人、補助人という三つの形態によって、判断能力が低下した人々に対して、状況に応じた柔軟な支援を提供する仕組みとなっています。これらの制度は、本人の判断能力や支援の必要性に応じて適切に選択されるべきです。
4.1 制度の利用状況
日本では、近年、認知症の高齢者が増加していることから、成年後見制度の利用が増加しています。特に後見制度の利用が多く、裁判所によって選任された後見人が被後見人の財産管理や日常生活を支援しています。一方で、補助制度や保佐制度の利用は比較的少なく、今後の普及が期待されています。
4.2 課題と今後の展望
成年後見制度には、手続きの複雑さや費用の問題が指摘されています。特に専門職後見人に依頼すると費用が高額になるため、家族が後見人や保佐人、補助人として選任される場合が多いです。しかし、家族が支援者として選任される場合、財産の管理や生活支援が適切に行われないリスクもあるため、専門家のサポートが求められる場面もあります。
また、制度の利用に対する知識不足や抵抗感から、必要な支援を受けていない人も多いとされています。今後は、成年後見制度の普及啓発とともに、より簡便な手続きや負担軽減策が検討されることが期待されます。
結論
後見人、保佐人、補助人は、判断能力が低下した人々を支援するための重要な法的役割を担っています。それぞれの制度は、支援を受ける本人の状況に応じて選ばれ、適切なサポートを提供することが求められます。まずは、ご本人の状況を確認し、医師等の判断を仰ぎましょう。

令和7年3月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
聖徳太子が残した「世間は虚仮なり。唯仏のみ是れ真なり。」という言葉について、現代の今の状況について当てはめて、考えてみたいと思います。
「不在者財産管理人」(ふざいしゃざいさんかんりにん)は、居場所が分からなくなっている人(不在者)の財産を保護し、適切に管理するために、家庭裁判所が選任する法的な役割を担う者です。長期間にわたって所在不明である場合、本人の財産が損なわれたり、権利が不利益を被ることを防ぐために、この制度が設けられています。以下では、不在者財産管理人の概要、選任方法、権限、役割、具体的な事例、制度の課題と今後の展望について説明します。
後見監督人は、成年後見制度における重要な役割を担う人物であり、成年後見人の行為を監督し、適正な運用がなされるように支援する役割を果たします。この制度は、精神的な障害などにより判断能力が不十分な成人(被後見人)を保護するために設けられたもので、後見人は被後見人の財産管理や生活支援を行います。しかし、後見人が自己の利益を優先する場合などの不正を防止し、被後見人の利益を守るために、後見監督人の設置が必要とされることがあります。本稿では、後見監督人の役割、設置の要件、職務内容などについて詳述します。